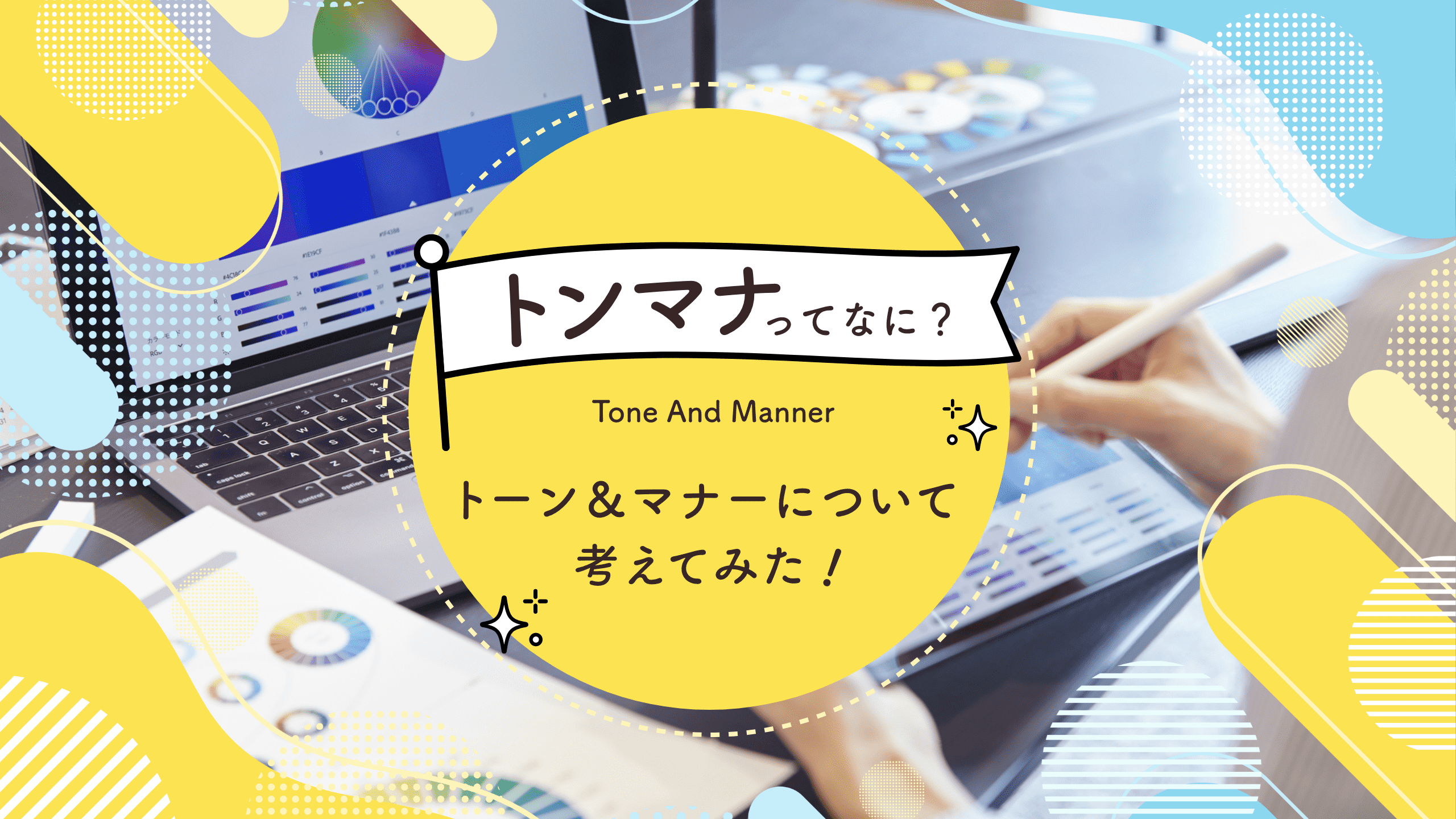こんにちは!最近せいろ蒸しを始めた、ディレクターのさわだです。
今回は、何気なく使っている業界用語について考えてみた、個人的な言語化訓練のための記事となっております。
お時間のある方は、ぜひ私の思考の整理にお付き合いいただけますと幸いです。
「トンマナ」が通じない
最近、友人とランチをしながら何気ない会話のやりとりで「それはトンマナ違うよね〜」と私が発言したところ、友人に「なにそれ???」と言われました。
この「トンマナ」という言葉。トーン&マナーの略ですが、確かにクリエイティブに携わる人しか使っていない言葉かもしれません。
雰囲気、などと同じ意味としてなんとなく使ってきましたが、実際に仕事中にもデザイナーさんから上がってきたデザインを見て「なんかトンマナ違うかも…」というときに言語化できないことが多々あるので、この機会にきちんとトンマナについて考えてみようと思います。
辞書で調べてみる
まずは、トーン、マナーという言葉をそれぞれ分解して、本来の意味から考えてみようと思います。
・トーン(Tone):音、音調。色調。物事全体から感じられる気分・調子。
・マナー(Manner):態度。礼儀。礼儀作法。
ふむふむ。辞書で調べると思考がすっきりする気がします。
デザインの文脈に落とし込んでみる
では次に、それぞれの言葉の意味をデザインの文脈に落とし込んで言い換えてみようと思います。
言い換えてみると、次のようになりました。
- トーン:クリエイティブ全体から感じられる印象や色の調子。
- マナー:クリエイティブ内で使われている要素のルール
このように整理してみると、例えば上がってきたデザインを見て「なんかトンマナ違うな」と思った時に、どこを見ればいいのかが明確になってきそうです。
①パッと見た時に全体から感じる印象や色の調子が、表現したい想いや持ってもらいたい印象と合っているか?
②使われているあしらいやモチーフ、文字のフォントやサイズ、余白などの要素のルールに統一感はあるか?
以上のような視点で考えてみれば、「トンマナを合わせる」ということができるようになる気がしてきました!
逆に言えば、そもそも表現したい想いや持ってもらいたい印象がきちんと定まっていないと、トンマナという考え方自体も成立しないということですね。
つまりトンマナとは、デザインの「印象」と「ルール」を統一することでブランドの世界観をかたちづくるもので、これが整っていると、伝えたいことがより明確になって、一貫したメッセージを届けることができるってことですね!!(急に早口ですみません)
イッパイアッテナのトンマナを考える
ここまできたら、トンマナが合っているか確認したくてしょうがない…!
というわけで、イッパイアッテナのコーポレートサイトのデザインが伝えたいメッセージと合っているのか検証してみようと思います。

トーン(クリエイティブ全体から全体から感じられる印象や色の調子)
ポップ/カラフル/明るい
かわいらしい
絵本みたい/子供っぽい
優しい/柔らかい
わくわく感
マナー(クリエイティブ内で使われている要素のルール)
全体的に丸いあしらい、角も丸い
猫かわいい、猫のモチーフ
文字の余白がちょっと広い
ひらがなが多い
ブルーナカラーで揃っている
検証
イッパイアッテナのミッションは「デザインと教養と想像力で世界を正解でイッパイに」。
この意味については代表が記事にもしています。
検証した結果、このコーポレートサイトはその想いを、Webデザインを通じて実現できているという結論に至りました。
まず、社名の由来が児童書『ルドルフとイッパイアッテナ』であることからもわかるように、イッパイアッテナは教養と想像力をとても大事にしているので、サイトデザインに児童書のような印象を持たせることで、教養と想像力を楽しく学べる環境が表現されているし、猫のモチーフを使うことで会社の世界観がより強く印象づけられています。
そして次に、イッパイアッテナが考える「正解」とは、「正しいことを押しつけること」ではなく、「正しい情報が、正しく、わかりやすく、必要な人の元に届くこと」。
全体的にポップで明るく柔らかいデザインにすることで、サイト内の情報が楽しく、親しみやすく、読みやすく、直感的にわかりやすく届くようになっているのかなと思いました。
答え合わせは、いつか会社でみんなに聞いてみようと思います。
まとめ
ふだん何気なく使っている言葉でも、改めてこうやって考えてみると奥が深いものですね。
最終的になぜか会社への理解も深まったような気がします。
せっかくブログを書ける環境が整っているので、これからもちょっとずつ言語化の精度を上げていきたいと思います。
では、今日はこれからせいろ蒸しの時間に入ります。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!