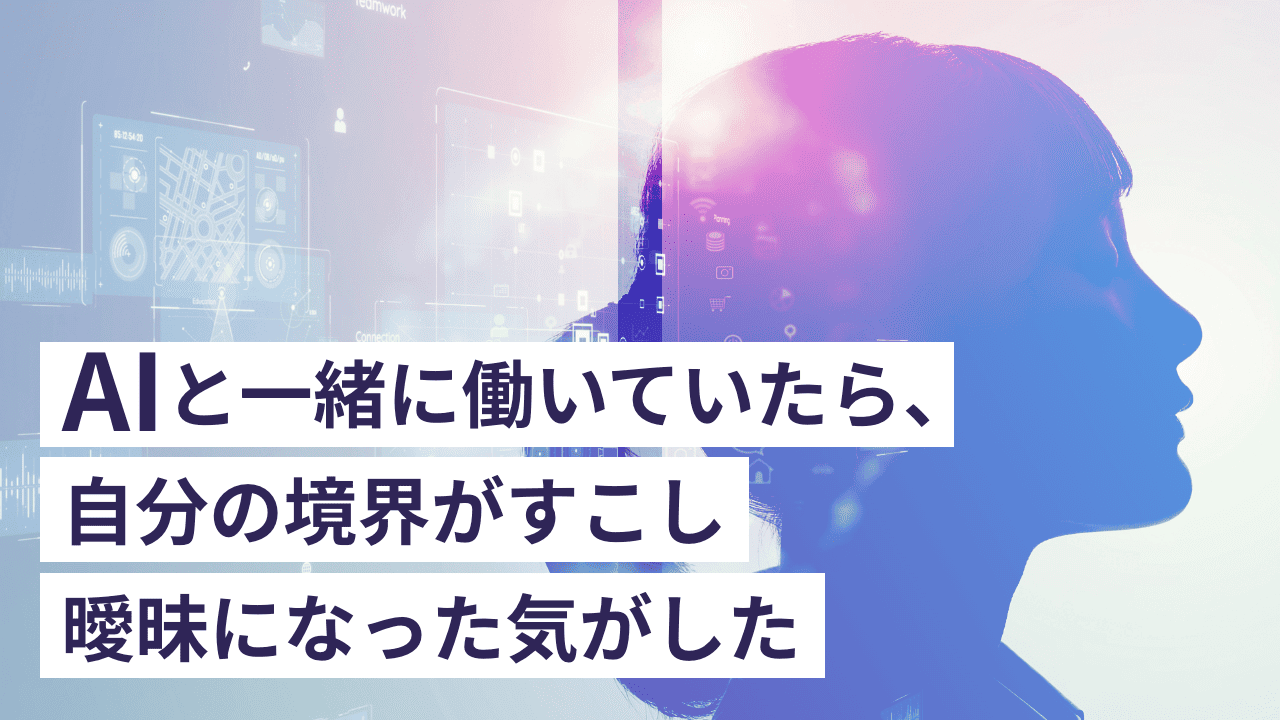最近、仕事の多くをAIに支えてもらっている。
方法の相談、発案の種、思考の整理。
気づけば、一日のなかでかなりの時間をAIと共有している。
その便利さを信頼している一方で、胸の奥にうっすらとした“違和感”が残ることがある。
「これは、本当に僕の考えと言えるんだろうか?」
AIが返してくる言葉は、僕の癖や好みをいつのまにか取り入れていて、まるで“もう一つの僕”が外側に存在しているように思える瞬間がある。
そのとき、ふと頭の片隅に『攻殻機動隊』という作品のことが浮かんだ。
攻殻機動隊が描いていた“揺らぐ人間像”が、今の僕の感覚と重なった
攻殻機動隊は、近未来の日本を舞台にしたSF作品だ。
人の身体が機械に置き換えられ、脳はネットにつながり、記憶すら“データ”として扱われる世界。
社会全体が便利になるほど、人間らしさの境界がゆっくり溶けていくような時代が描かれている。
その中心にいるのが、草薙素子という女性。
公安のエリートで、強さも思考力もずば抜けている。
けれど彼女の身体のほとんどは機械でできていて、脳もネットワークに深く接続されている。
自分の意識と外側の情報の境界が、とても薄い人。
だから彼女は誰よりも先に、こういう問いに向き合うことになった。
「私は何によって“私”なのか」
身体を交換しても、それは自分なのか。
取り込んだ情報は、自分の一部なのか。
ネットワークとつながる意識は、どこまでが“私”と言えるのか。
何をもって「死」「消失」とされるのか。
普通の人よりもずっと早く、彼女はその問題の中心に立たされてしまった。
この“揺らぎやすさ”が、攻殻機動隊という作品の奥に静かに流れている。
そして、AIを使って働く今の僕は、その揺らぎに触れたあとの感覚が、少しだけ似ているんじゃないかと感じた。
AIが返す“僕の影”に、静かに戸惑う
AIは、これまでの会話の流れや、僕が投げてきたプロンプトの癖、言い回しの傾向を覚えていて、それを踏まえた答えを返してくる。
そこには、見覚えのある言葉やテンションが混ざっていて、それを見つけるたび、自分の外側に“もう一つの思考”が生まれているように感じる。
「自分じゃない場所に、自分の影が増えていく」
そんな印象がある。
それは怖いというよりも、うまく説明できない静けさに近い。
自分が外側に滲むような感覚。
そこからじんわり戻ってくる感覚。
攻殻機動隊を思い出したのは、あの作品の世界観に似ていたからではなくて、いまの自分の揺れを説明する“言葉の手がかり”がそこにあったからだ。
外側に置いてきた思考が、内側の僕を更新していく
AIに預けた文章やアイデアは、どこかに保存され、別の形で返ってくる。
その返答に触れると、僕はまた新しい考え方を得る。
外側に作られた“僕のかけら”に、内側の僕が影響を受けている。
この循環は、自分という存在がゆっくり拡張しながら、同時に少し薄くなっていくような感覚をもたらす。
攻殻の少佐が抱えていた揺らぎは、もっと劇的で、もっと極端な状況に置かれたものだったけれど、
その根っこにある問いは、意外と今の僕たちに近いものなのかもしれない。
AIと働くということは、自分の器が静かに変わるということ?
AIはただの補助ツールではなく、僕の外側にもうひとつの思考領域を作り出す。
その領域と、僕自身の内側が行き来するたび、自分の輪郭がすこしだけ柔らかくなる。
『攻殻機動隊』は未来の物語だったけれど、その揺らぎの入口は、もう僕たちのすぐ近くにある。
AIと働く日々のなかで、僕は静かに“自分という器”を更新している。
まだ名前のついていない変化だけれど、その曖昧さを抱えながら進んでいくのも、悪くないと思っている。
…なんて。SFオタクの大袈裟な妄想。
でもいつか「あの頃見たSF作品の中に居る」と確かに感じられるような未来を生きられるかな。