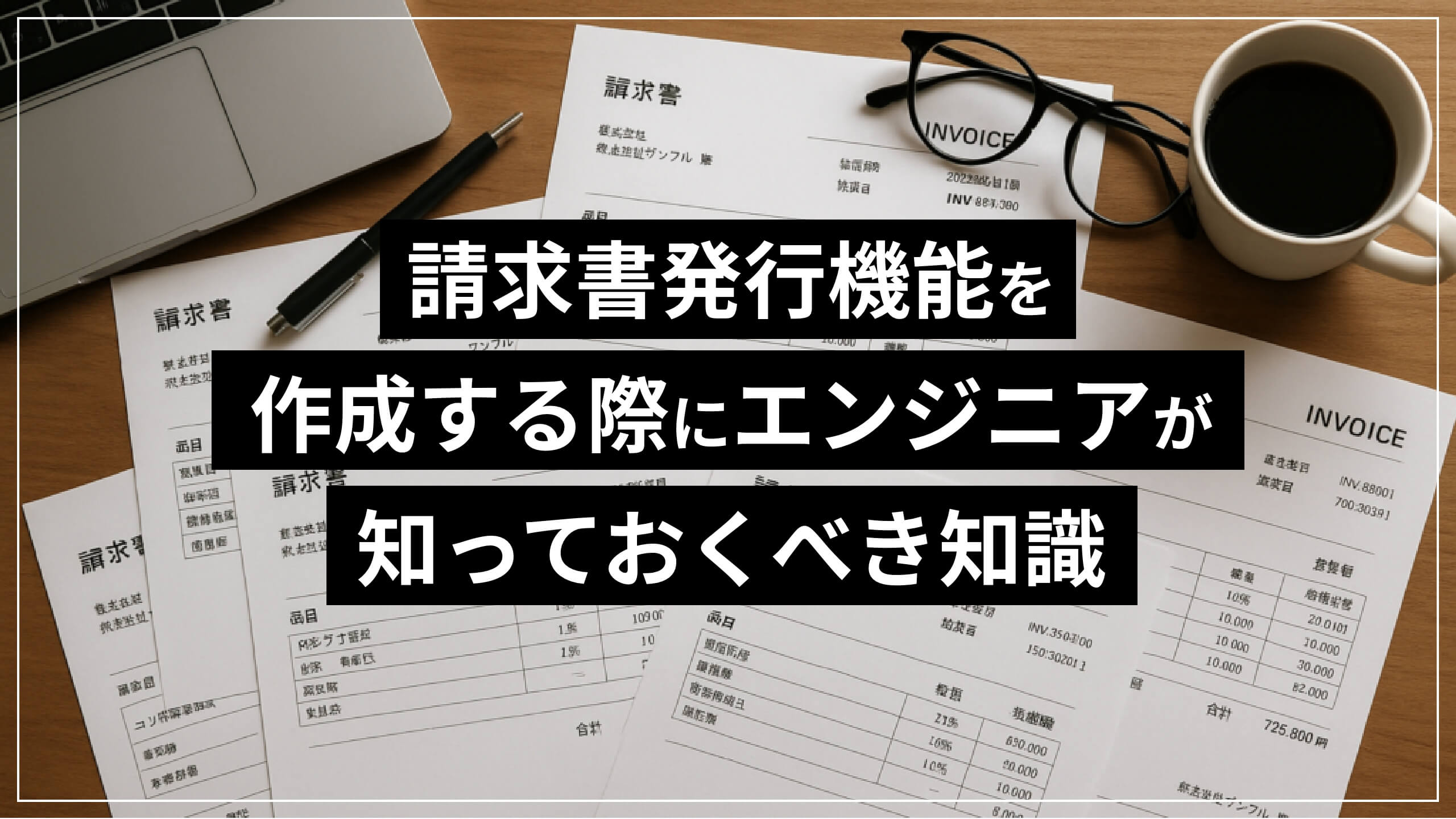こんにちは。気づけば8月も終わってしまいそうですが、まだまだ暑い日々は続きそうですね。私はアイスが好きでついガリガリ君を食べてしまうのですがお腹を壊さないように気を付けたいと思います。
最近の案件では請求書の発行機能を付けるといったものが、なぜかよく回ってきます。事業の売り上げのタイミングや計上すべき項目をまとめたりもするのはディレクターかもしれませんが、細かい項目はエンジニアでも理解しておくと開発スピードが格段に上がります。複雑な請求だと、ちょっとした設計の穴を見つけたりすることもできたりすることもあるので私が見ているポイントをいくつかあげたいと思います。
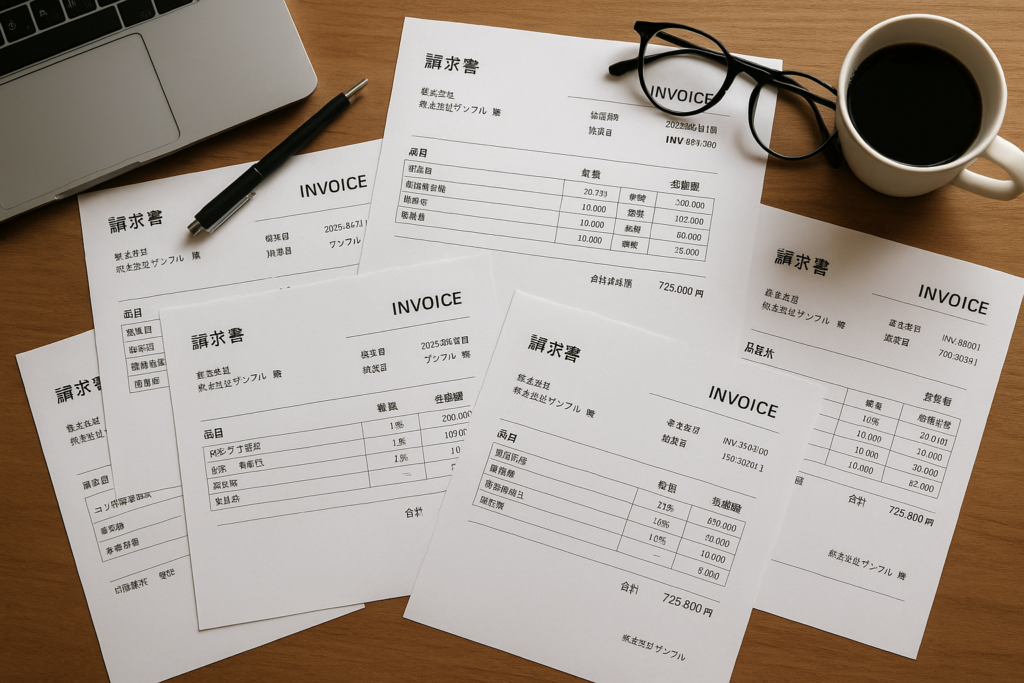
売上はいつ計上されるのか、いつ入金されるのか
請求書は「商品やサービスに対する対価が発生した日」で売上計上して作成します。このいつ売り上げが発生したかというのをシステムでいかに作り上げるのかポイントかと思っています。また大きな問題が入金がいつされるのかといった問題です。簡単なものであれば売上発生月から翌月末といったものは多く存在しているのですが、このユーザーは翌々月末、このユーザーは翌月末…と、いわゆる支払いサイトがユーザーによって変わってくるケースも数多く存在しています。この場合はユーザー単位で支払いサイトを保管する必要があるので設計前の要件定義の段階で計上のタイミングと入金はいつされるのかを把握しておきましょう。
消費税は10%だけではない
私たちの生活の中で消費税は10%のイメージが強いと思います。(2025年現在) 一部商品や新聞には軽減税率で8%が計上されたりもしますが、課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引といった取引ごとの区分けが発生します。例えば寄付金であれば課税対処外といった処理になります。請求書に発生する項目がどのような項目で、税率や区分けをしっかりと把握しておきましょう。
インボイス制度への対応
適格請求書発行事業者しか「仕入税額控除」を受けられなくなったため、請求書には登録番号を必ず記載する必要があります。このようにインボイス制度に適した請求書には下記要件が必要です。
1.請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号
2.取引内容
3.取引年月日
4.税率ごとの合計金額と消費税額
5.請求を受ける事業者の名称
さきほど消費税の話で税率には様々あるといった話をしましたが、インボイス制度に適した請求書の発行には、それに伴うフォーマットも必要となります。
まとめ
請求書はただのフォーマットを埋めていくものではなく、売上・経費・消費税・インボイス制度などの会計知識とつながっています。どのフォーマットで出力するのかなどの要件もありますが、会計知識とともに請求書を作ってみると、奥の深さに楽しく作成できるかもしれません。納期さえなければ…ですが。